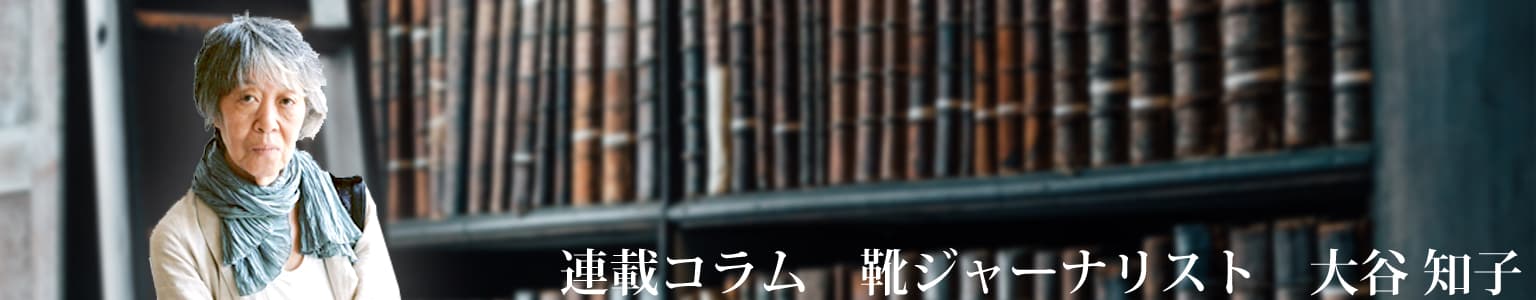連載93 ハイハイしましょ。
「できちゃいました。目が離せなくなります」。
ちいくんのママが、こんなことを言いました。
ちいくんは、孫のそうちゃんの弟。
満7カ月を少し過ぎたところですが、つかまり立ちができるようになったというのです。
「母子健康手帳」には"保護者の記録"という項目がありますが、"9〜10か月頃"のページに"つかまり立ちをしたのはいつですか。"という質問があります。
これからすると、つかまり立ちは、9〜10カ月が標準のようです。
ネットでも検索をしてみたところ、「早ければ6カ月頃、通常は8〜11カ月頃が目安」とありました。
個人差がかなりあるようですが、ちいくんは、早い方に入るのですね。
赤ちゃんの運動能力の発達は、まず首がすわり、次に寝返り。
すると腹ばいで体をずって動くようになり、これに手足がついてハイハイとなり、次が、つかまり立ち。
そして、支えがなくても立てるようになり、ついによちよちと足を進め、歩き始めます。
そしてちいくんができるようになった、つかまり立ちについて近年、よく聞くようになっているのが、ハイハイをせず、いきなりつかまり立ちをする赤ちゃんが増えているということです。
では、これは発達が早いと喜ぶべきことなのでしょうか。
どうやら違うようです。
ハイハイをせず立ってしまうと、歩けるようになってから影響が出るようです。

●ハイハイしてみると分かります
では、ハイハイには、どんな効能があるのでしょうか。
「ハイハイ(這い這い)」と一口に言っていますが、発達段階によって三つの種類があります。
まずできるようになるのが、うつ伏せ姿勢のまま体をずりずり動かして進む「ずり這い」。
次が両腕を伸ばし、両手と膝で体を支えて進む「四つ這い」。
これが私たちが「ハイハイ」と見なしている一般的な形です。
そして最後が膝を伸ばし腰を高い位置に持って来て、両手と両足の指を使って進む「高這い」です。

これが、どんな運動なのか、自分でやってみると分かります。
四つ這いで進んでみてください。
すっごくたいへん。
疲れます。
なぜかと言うと、手、足だけではなく腹筋、背筋と各種の筋肉を使う全身運動だから。
また、前に進むには手足を交互に動かし、体を3点で支える瞬間があります。
つまり、3点支持でも倒れないようにバランスを取る必要があります。
また、高這いは、さらにたいへんです。
四つ這いよりも不安定なので、バランスを取る必要がさらに増し、腕、腹筋、背筋をより使い、また床を足の指で掴んで進むという動作も必要です。
つまりハイハイによって、二つの足で立ち、歩くための筋肉、そして体幹を鍛え、バランス感覚を養っているのです。
この他にも、目で認知したものに向かって動く、言ってみれば認知運動能力といったものを養い、また手と足を動かすことで脳の発達も促しています。
ちいくんは、つかまり立ちができるようになってからの方がハイハイが活発になっています。
つかまって立てそうなもの、例えば座卓を見つけると、それに向かってハイハイで進み、端につかまって立とうとします。
ママが「目が離せない」というのが分かります。
失敗して立てなかったら、テーブルに顎をぶつけてケガをしてしまうかもしれないのですから。
ママが注意して見ているから、ちいくん、しっかりと歩くために頑張ってね。
靴を用意して待ってます。